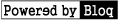| ← | 2025年5月 | → | |||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|
2 | 3 | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 最近のコメント |
| まーぶみっく on 友達百人? マチルダ on 友達百人? まーぶみっく on 友達百人? マチルダ on 友達百人? |
| 携帯で読む |
| URLを携帯に送る |
| ブログ内検索試験 |
|
|
| 本日 | 39 |
| 昨日 | 230 |
| 累計 | 1370330 |
| 久しぶりの更新 |
| なんだかんだと、トウモロコシは、無事に8月下旬に収穫。 2回に分けて収穫したが、最適収穫期間が五日しかなかったのにはびっくり。でも旬を過ぎてもスーパーで売っているのよりは美味しい。 ナスは美味しかったけど、よく考えたら好きじゃないので8月末に抜いてしまった。 ミニトマトのぷるるん?なんとかは皮が薄くて確かに美味しかった。 きゅうりも最後の2本を収穫して切り落とした。 なんで、ナスもトマトもキュウリも止めたかと言うと、太ネギが夏を超えたら無茶苦茶美味しいのだけど、被せる土が無くなったから(汗 暑さのせいかミョウガも8月頭に収穫し化成肥料をお礼肥。 セルトレイも買ったし、さてタマネギと進むには少し早いので、コマツナとホウレンソウを播種。 トイレットペーパーを使ったシダーテープは楽だったがPVAだけで作れないかな? |
| 忘れるとこだった |
| で概ね、2から3葉になったトウモロコシを定植した。 品種は確かゴールドラッシュ90、5月末に播種して、6月頭に発芽したやつ。 9月くらいには運が良ければ収穫できるはず、運が悪いと台風で全滅。 と、言うことは、7月半ばか8月頭には玉ねぎの苗を始めないとならない。 セルトレイが有ったはずだが行方不明、持っていたのは確か128穴だったような。。。 玉ねぎは200穴セルトレイで良いはずだが、耕作面積から苗の上下捨てても100苗で良いのだが、苗の収量が解らないので早生種・中晩成種で100ずつなら200穴全部だな。 そんで、二度目のウリハムシの襲来。キュウリが収穫時期なので週末まで様子見して、キュウリとカボチャに殺虫剤かな? |
| ネギって手間が掛かるの? |
| 梅雨に入って、気温が下がったら、案の定ネギにさび病の初期か、小菌核腐敗病の初期な気が、スリップすではないぞ。 まあ、2週間たったので、そろそろ薬剤を換えてもう一回、ダコニール1000とエスマルクDFを撒く。 ゼンターリ顆粒水和剤とエスマルクDFだが、なんで二種類買ったかよくよく考えたら、菌種違いだった。 エスマルクは亜種クルスターキ系統、ゼンターリはアイザワイ系統、あれ?ネギに撒くならゼンターリじゃん。。。 気を取り直して、カボチャのハダニは手で払って水で洗い流す。下葉2枚だけだからこれでいいや。 |
| 積算温度 |
| 積算温度とは植物が発芽したり、収穫できたりするまでに必要な累積環境温度だ。 バレイショの次に何やろうか考えてたら、秋からは今年高い玉ねぎをやるようお願いが有った。 玉ねぎは15cmマルチで早生と日持ちするのを合わせて1畝、もう2畝は葉物か大根かな? そうなると6月から9月くらいでできる他の何か、、アブラナ科の葉物は虫がね、ホウレンソウはこの前やったし、オクラは買ったほうが安い。 取り立てが美味しいに限定すると、トウモロコシとエダマメかな? で、昨年10苗で実の入りの悪かったにリベンジでと月曜の夜に種を撒いたら金曜の夜に既に発芽率80%? 確か、170℃くらい必要だったはずだがなぜ? 積算温度は (平均環境温度−植物が必要な最低温度)x日数 で計算する。 初日はペットボトルに45℃のお湯を入れて加温したし、冷房のない室内で20〜25℃をキープして、最低温度の10℃を引くと積算温度70℃くらい。 慌てて文献を探しまくったら、一日の温度の変化で最低温度+10℃をキープすると最短70℃で発芽との文献が有って理解した。 要するに4月に路地撒きで地温が10℃とかに成ると休眠しちゃうみたい。逆に育苗箱や発芽器でなどで昼間と同じ温度をキープしていると極端に短くなるらしい。 納得したが、台風シーズンに成るので中晩成の抑制栽培を選んだが、白黒マルチは200mで3000円店舗販売か、50mで2000円送料込みしか選択肢が無いのがなんだかな。 ガソリンが高いので、その辺の種苗店やホームセンター、農協を回って探すと逆に割高になる。 |
| 県の緑政部自然環境保全課か市の水みどり環境課か? |
| たまたま見つけたキク科の特定外来生物っぽい黄色い花。 花弁の黄一色と外周のギザギザは完全に一致、スマホのアプリのハナノナも悩んでいてオオキンケイギク70%とか表示される。 仕方がないので自分で同定: ・花弁の黄一色 〇 ・舌状花 〇 ・管状花 ? ・根生葉が多い 全く無い × ・根生葉が小葉裂片 無いのだから無い × ・茎葉が少ない 茎葉しかない × ・茎葉が対性 バラバラ × ・葉に毛が有る 無い × ・葉が微妙に細い △ 結果発表: ホソバハルシャギク それで、ハルシャギクで決定されたハナノナに、ホソバハルシャギクと教えようとしたが、使い方がわからない。 |